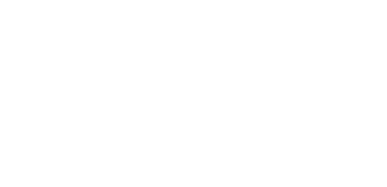執筆:HUB Tokyoファウンダー マネジメントチーム ポチエ真悟
第一印象、「なんだが物足りない」
日本で暮らすのは20年以上ぶりなので、ほとんど友達もいなく、もちろんネットワークやパートナーもいなかった。最初の数ヶ月は意欲的に色んなミートアップやピッチイベントに参加し、研究し、仲間を捜した。
ロンドンで見たような、沢山の熱い奴らが死にものぐるいで頑張っていたのをみて、少しなじみを覚え、自信がついた。ロンドンから来たという事で、たくさんの面白い人達に紹介してもらい、最近数億も調達できるほど事業を成長させた起業家達にも出会えた。
だが、そうやって面白い人たちにであえて幸運であると同時に、今でも変わらない第一印象がある。
日本のスタートアップ業界を見ていて物足りない。全く満足できない。当たり障りないメッセージでどこかで見た事ある様なサービスを発表し、ニュースに飢えたメディアがそれについてチラッと書き、ソーシャルメディアのタイムラインで「◯◯◯に△△△(有名企業)と共に紹介された」と喜んでいる。他企業の名を借りて、自社の事業内容が説明されていて、喜んでいいのだろうか?それで良いのか?
革新的なビジネスを作ることが、決して簡単ではないことはHUB Tokyoを含め、過去の起業経験からわかる。だが、どうしてここまでみんなハーモニーを求めるのか?どうしてGame Changerが現れないのか?
「日本の起業家は辛い」のは分かる
Game Changer が現れない理由について考えた時、社会的価値を生み出していない中間業者の数の多さ(これは独自で解決できる問題でさえ中間業者をかませないと話が進まない仕組みを助長している)、そして、機能していない行政や振込手数料で食っている金融機関、国際的事業に必要なスキルやイノベーションについて何も教えてくれない教育、各主要業界の慢性的な独占市場、など暗くなるような理由ばかり目につき始め、あきらめかけた。日本で起業するということは、他の先進国での起業に比べて、かなりハードルが高いのは確かだ。
そのような状態で、HUB Tokyoの起業を手伝うようになり、ファウンダーとして関わるようになって、一つ重要な事を思い出した。
行政や、仕組み、その環境に「足りない物」など気にしていたらきりがない。決められた枠の中で仕事をし、誰にも逆らわず、与えられた「市場」で仕事をし、儲けていきたいのであれば大企業に勤めていればいい。
スタートアップにとって悪環境の中で起業し、世界を変えられるような仕事をすることの方がチャレンジとしては面白く、やりがいがあるのではないか。
スタートアップのプロセスの中にある「市場を確定する」(Validating the market)という作業は、決して既存市場で自分の取り分を増やすために、周り人の顔を立てながら「調整する」ことではないと思う。
日本の「優等生」な起業家達
HUB Tokyoを設立し様々なスタートアップの話を聞き、起業家育成をし始めて思うことがある。日本の起業家の多くがお行儀良すぎる。
日本にも沢山の優秀な起業家が居るが、多くがもっともなブログを書き、本を出版し、あちこちで講演をしているようだが、ほとんどが「優等生」過ぎて、刺激が無く、もの凄く無難な話ばかりする人達だ。それで良かったのか?世間体ばかり気にしていて、世の中を変えられるのか?
日本のビジネス文化を理解していると自称する海外のビジネスマンが、日本について説明する時に良く持ち出すことわざは「出る杭は打たれる」や「石橋を叩いて渡る」だ。
私が驚いたのは、日本の起業家たちは、ライバルと正面からぶつかるようなメッセージは出さず、(極端に言えば)ライバルやその市場の大手と並んで比べてもらえるようなメッセージを発信する、ということだった。あとは営業力で何とかしようとするパターンだ。これでは、スケールしにくいに決まっている。
万人に理解を求めるな
起業家が発信するメッセージが明確であることは必要不可欠だが、万人に理解を求めるとメッセージはぼやける。特に日本でよく見る光景に、周り、特に「先輩」的な位置におかれている企業からの理解を求める、というのがある。
「敵を減らせ」という考え方は日本文化 に深く根付いているように思える。敵は少ないに越したことはないが、何かを変えたいとなった場合、成功できるのは敵が少ないからではなく、その人を大切にしてくれるサポーターがたくさんいるからだ。そのサポーター達は、その人が発信するメッセージに好感を持ち、自分ごとのようにその人のメッセージを広める。
敵を作りたくないといった考え方は、イノベーションを妨げる。理解できない人間、理解したくない人間を説得する時に必要とするエネルギーの量は膨大である上に、理解してもらえたところで、サポーターにまでにはなってくれない。
日本の消費材業界のほとんどが、同業者とうまくやっていくために価格調整を行い、競業阻止をとるような動きを取っている。そして、時々、日本の起業家たちにもそういった動きを見る。これが小さな市場を共に暖めていこうという動きで済めば良いが、価格や内容にも差を付けず、競争を避けてしまうと差別化が難しくなる。敵は少なくて済むが、事業の進路を独自で設定しにくくなり、表現の自由を失う。表現の自由を失った起業家が「変革を求める」のはほぼ不可能だろう。
自分がいる市場を見直せ
日本の市場が飛び抜けすぎたアイデアを受け入れないのだとしたら、世界を見れば良い。日本以外の市場は、お行儀などあまり気にしない。その起業家が本気であり、商品が良質で、価格がニーズに合い、なおかつ、消費者が求めている変化や問題解決を、その商品が与えることができるのであれば、そのようなコミュニティーで活動することがもっとも効率的だと思う。
お行儀をあまり気にせず日本でやっていく方法もあると思う。タフなことのように思えるかもしれないが、一つだけ、自分の経験からわかっていることがある。お行儀が悪い分、自分の言動に責任を取り、サポーター達には常に誠実で敬意を持って接していると、お行儀良くしていた時よりも多くの仕事を達成でき、もっと多くのサポーター達に囲まれるようになる。
お行儀悪くなれと言ってるのではない。
起業家がにらまれ始めた時は、なにかが変わろうとしている時だ。でも、そうなっても孤独ではないということを覚えておいてほしい。